子どもの昼寝の必要性を解説!質の高い昼寝を行うには?

「子どもにとってお昼寝の必要性は高いのだろうか?」「子どものお昼寝の質を高めるポイントがあるのなら知りたい!」など、幼いお子さまを育てるパパ・ママで、子どものお昼寝について気にされている方は多いです。
実際、子どものお昼寝の必要性は高く、質の高いお昼寝をすることで、さまざまな効果を得られます。
お昼寝の時間などは個人差が大きいですが、子どものペースに合わせたお昼寝は、心身の健康を保つ上でも重要です。
このページでは、子どものお昼寝の効果・お昼寝の質を高めるポイント・年齢別のお昼寝の時間の目安・スムーズに入眠するポイントなどについてご紹介します。
もくじ
子どもにとって必要性が高いお昼寝から得られる効果
子どもにとってお昼寝の必要性は高いです。それは、お昼寝から以下のような効果を得られるためです。
・心身の健康保持
・免疫力の向上
・学力アップ
・情緒の安定
1つずつ、見ていきましょう。
心身の健康保持


子どものお昼寝の効果の1つ目は、心身の健康保持です。
子どもは遊びに熱中すると、本人も気付かないうちに疲れを溜めてしまうことがあります。疲れた状態で運動や遊びを続けると、ケガをしたり、夜になって体調を崩したりすることにつながる場合があります。
また、眠くなると自律神経が乱れ、イライラして攻撃的になったり、不安な気持ちが強くなったりすることもあるでしょう。
慢性的な睡眠不足は、身長が伸びにくくなったり、成人後の生活習慣病などの病気の確率を高めたり、子どもの身体的な成長に影響を及ぼします。
子どもの心身の健康を保持し、毎日を元気で前向きな気持ちで過ごすには、子どものお昼寝はとても重要なのです。
免疫力の向上


子どものお昼寝の効果の2つ目は、免疫力の向上です。
お昼寝をすることで、身体的・精神的な疲れが癒されるだけでなく、睡眠中に分泌される「メラトニン」というホルモンにより、細胞の免疫力低下を防ぎ、抵抗力が向上すると言われています。
特に幼児期はメラトニンが最も多く分泌される時期です。短時間のお昼寝でも免疫力に影響するため、インフルエンザや風邪が流行する季節などのお昼寝は特に効果的と言えます。
学力アップ


子どものお昼寝の効果の3つ目は、学力アップです。
アメリカのマサチューセッツ大学、心理学者Rebecca Spencerの3~6歳の未就学児を対象にした研究では、「お昼寝によって脳の記憶領域が整理されるため、お昼寝は記憶力向上に効果がある」という結果が出ています。
お昼寝で疲れがリセットされることで、絵本を読んだり学習したりする時の集中力が上がり、結果的に学力アップも期待できます。
子どもは遊びの中で多くのことを学んでいるので、眠気のないスッキリした状態で活動的に遊ぶことが重要です。
アメリカの複数の大学では、睡眠と学習の関係性の研究が進んでおり、睡眠は記憶力だけでなく、物事を推測する力や新しい知識・スキルを身につける力も向上させることが分かっています。
出典:Naps Nurture Growing Brains | Science
情緒の安定


子どものお昼寝の効果の4つ目は、情緒の安定です。
子どもは起きている間に、脳にさまざまな刺激を受けています。
脳に疲労が溜まると、落ち着きがなくなり、感情を上手くコントロールできなくなるなど、情緒が不安定になります。
そうすると、かんしゃくを起こしたり、グズグズしたりすることが続いてしまいます。
刺激で疲れた脳をお昼寝でしっかり休めることで、機嫌良く過ごせる時間が増えると言えます。
必要性の高いお昼寝の質を高めるための5つのポイント
お昼寝は子どもにさまざまな良い効果をもたらしますが、深くぐっすり眠れるようお昼寝の質を高めることも重要です。
お昼寝の質を高めるポイントは以下の5つです。
・午前中はたっぷり遊ぶ
・子どもに無理強いしない
・部屋の環境を整える
・睡眠時間を調整する
・寝る前に電子機器を与えない
1つずつ、見ていきましょう。
午前中はたっぷり遊ぶ


お昼寝の質を高める1つ目のポイントは、午前中はたっぷり遊ぶことです。
散歩・ボール遊び・かけっこなど、体をよく動かすことで、入眠をスムーズにするだけでなく、お昼寝の質を高めることができます。
特に晴れている日は、日光を浴びると良いでしょう。
日光を浴びると、脳を覚醒させる「セロトニン」というホルモンが分泌されると言われています。
午前中にセロトニンが分泌されることで、お昼寝の間に免疫力の向上や成長の手助けになることが期待できます。
子どもに無理強いしない


お昼寝の質を高める2つ目のポイントは、子どもに無理強いをしないことです。
お昼寝をさせたいのに、子どもが全く寝てくれないという日もあるでしょう。
横になるだけでもある程度効果があるので、その場合は「目を閉じて静かに横になるだけでも大丈夫だよ」などと声をかけ、子どものペースに合わせるようにします。
「子どもが寝ている間に夕食の準備をしておこう」などと予定を立てていると、「なんで寝てくれないの?」と焦ったりイライラしたりすることもあるかもしれません。
親は「お昼寝をしない日もある」となるべくどっしり構えて、子どもに合わせた柔軟な対応を心がけることが重要です。
部屋の環境を整える


お昼寝の質を高める3つ目のポイントは、部屋の環境を整えることです。
部屋が明るすぎると子どもの眠気が覚め、子どもはなかなか寝付くことができません。
カーテンを閉めたり、電気を消したりして、部屋を暗めに保ちましょう。
パパやママが同じ部屋で別の作業をする場合も、照明は暗めにしておき、手元だけ照らすなどの工夫をします。
また、温度設定にも注意が必要です。寒すぎたり暑すぎたりすると、体調を崩す可能性があります。
睡眠中は体温が下がるため、夏場でもタオルケットなどをかけて体を冷やさないようにしましょう。
大人の肌の感覚やエアコンの温度設定で温度を判断すると、実際の温度と異なる場合もあるので、温度計で確認すると確実です。
睡眠時間を調整する
お昼寝の質を高める4つ目のポイントは、睡眠時間を調整することです。
お昼寝が長くなりすぎると、体内時計が機能しにくくなり、夜に眠れなくなってしまうことがあります。
この状態が続くと慢性的な寝不足にもつながります。
お昼寝の時間を調整し、夜に目が冴えてしまって夜更かしするという悪循環に陥らないようにしましょう。
寝る前に電子機器を与えない
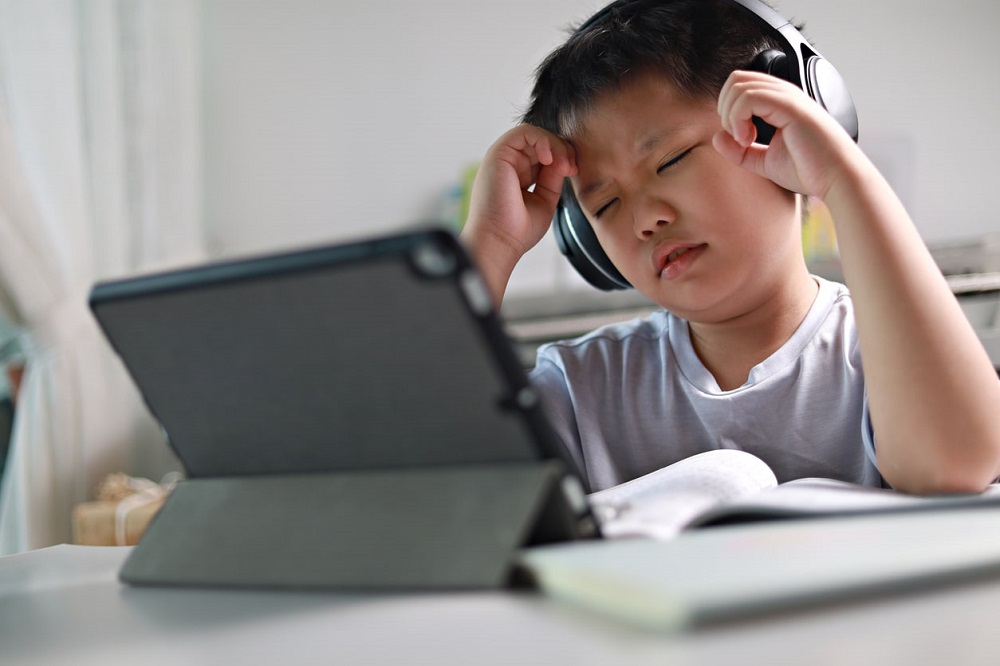
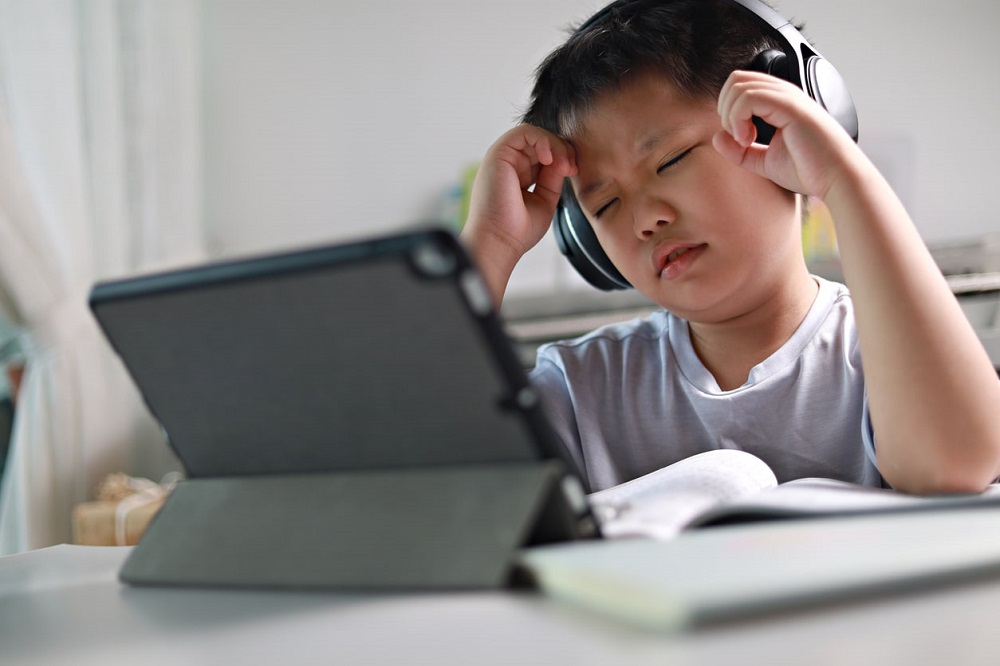
お昼寝の質を高める5つ目のポイントは、寝る前に電子機器を与えないことです。
電子機器の強い光やブルーライトを見ると、寝付けなくなるだけでなく、眠りが浅くなる可能性があります。
お昼寝の直前はスマートフォンやテレビなどを見せないようにし、絵本を読み聞かせたり、静かな音楽を聴かせたりして、スムーズに入眠できるようにしましょう。
子どもに必要性が高いお昼寝の時間の目安
では、子どもにとって必要性の高いお昼寝の時間の目安はどれくらいなのでしょうか?
お昼寝の時間が長くなりすぎると夜の睡眠に影響するため、適切な時間でお昼寝することが重要です。
ここでは、年齢別にお昼寝の時間の目安をご紹介します。
・0歳児
・1~2歳児
・3歳児
・4~5歳児
・6歳児
1つずつ見ていきましょう。
0歳児
0歳児は月齢によってお昼寝の時間が変わります。
生後まもない赤ちゃんは、1日のほとんどを寝て過ごします。
生後3ヶ月ごろまでは昼と夜の区別なく、3~4時間おきに目を覚まし、短い睡眠を繰り返します。
生後3〜6ヶ月ごろからは徐々にまとまった睡眠をとるようになり、長く起きていられるようになります。
この頃から夜の睡眠とは別に、午前に1~1.5時間、正午ごろに2時間、午後に30分〜1時間程度を目安にお昼寝をすると良いでしょう。
「ママの抱っこじゃないと寝てくれない」「布団に移動しようとするとすぐに目覚める」など、睡眠に関する悩みも多い時期です。
「お昼寝の時間が多い・少ない」など個人差が大きいので、目安の時間にとらわれすぎないようにし、赤ちゃんが機嫌良く過ごしているかどうかを確認するようにしましょう。
1~2歳児
1~2歳児のお昼寝の時間の目安は、1.5~2.5時間程度と言われています。
1~2歳児は徐々に体力もつき、0歳児ほど睡眠時間を必要としなくなる傾向があります。
また、お昼寝を複数回に分ける必要が低くなりますが、子どもによって個人差は大きいです。
例えば、1時間程度でも疲れを癒やせる子どももいれば、2.5時間程度お昼寝が必要な子どももいます。
子どもの体力や家庭の生活習慣にもよりますが、夜の睡眠に影響しないよう、正午前後にお昼寝の時間を設け、遅くても15時までには起こすようにしましょう。
3歳児
3歳児は、お昼寝を必要としない子どもが増えます。
夜にたっぷり寝ていて、昼間に眠気を感じていないようなら、無理にお昼寝をさせる必要はありません。
一方で、日中いつもより活動的に過ごしたり、本人が眠そうにしたりしている場合は、夕方に1時間程度のお昼寝をさせましょう。
4~5歳児
4~5歳児は、ほとんどの子どもがお昼寝を必要とせず、1日中活動的に過ごせるようになります。
ただし、午前中に体を活発に動かしたり、夏場にプールに入ったりして疲れが見られる場合は、短い時間でお昼寝をさせましょう。
短時間であれば、夜の睡眠への影響も心配ありません。
6歳児
6歳児の1日の理想の睡眠時間は10~12時間です。夜は21時には寝るようにし、お昼寝ではなく、夜のまとまった睡眠でこの時間を満たします。
しかし、小学校入学の年齢でもあり、入学直後は緊張感から疲れが溜まりやすくなる子どもも多いです。
慣れるまでは帰宅後に短時間のお昼寝をし、疲れを溜めないようにしましょう。
子どもにとって必要性が高いお昼寝をスムーズに行うためのポイント
子どもにとって必要性が高いお昼寝をスムーズに行うためのポイントは、気持ちを落ち着かせ、眠気を誘う環境を作ることです。
その具体的な方法は、以下の通りです。
・室温や明るさを適切にする
・添い寝する
・優しくボディタッチをする
・子守唄を歌う
・お気に入りのおもちゃを近くに添えてあげる
1つずつ、解説します。
室温や明るさを適切にする


スムーズなお昼寝のポイントの1つ目は、室温や明るさを適切にすることです。
・暑すぎないか、寒すぎないかを確認する
・部屋のカーテンを閉めて、なるべく暗い環境にする
上記のように室内の環境を整えることで、子どもは快適に入眠できます。
添い寝する


スムーズなお昼寝のポイントの2つ目は、添い寝することです。
添い寝することで、温もりを感じてリラックスできます。
子どもは身体的にも精神的にも居心地の良さや安心感を得られるため、スムーズに深い眠りに入ることができます。
優しくボディタッチをする


スムーズなお昼寝のポイントの3つ目は、優しくボディタッチをすることです。
子どもの体に手を添えたり、トントンと優しくタッチしたりすることで、日中活動的に行動していたところから徐々に落ち着くことができ、眠気を誘うことにつながります。
保育士さんがお昼寝の時間によく行う方法でもあります。
子守唄を歌う


スムーズなお昼寝のポイントの4つ目は、子守唄を歌うことです。
毎日のお昼寝の際に子守唄を歌ってあげることで、そのリズムやメロディが聞こえるとお昼寝の時間だと認識し、自然と眠くなるようになります。
子守唄は高音域でスローテンポな曲を選ぶのがポイントです。オルゴールのような優しい音楽をかけるのも良いでしょう。
赤ちゃんの場合は、抱っこをして音楽に合わせてゆったりと揺らしてあげると、スッと寝てくれるケースが多いです。
お気に入りのおもちゃを近くに添えてあげる


スムーズなお昼寝のポイントの5つ目は、お気に入りのおもちゃを近くに添えてあげることです。
好きなぬいぐるみなどと一緒に横になることで、安心して寝入る子どもは多いです。
おもちゃではなく、ずっと使っているお気に入りのタオルやママのハンカチなどで安心するケースもあるでしょう。
なかなか寝たがらない子どもには、お昼寝の直前まで遊んでいたおもちゃを布団に持っていくことで、そのままスムーズに寝入ることもあります。
ここで、お昼寝時におすすめのおもちゃを3つご紹介します。
ワーリー スクイグズ


ワーリー スクイグズは、花のような形状の遊べる歯がためで、クルクルと回したり握ったりして遊ぶことができます。
音が鳴らないので、回したり噛んだりしているうちに寝てしまうこともあるでしょう。シリコン製で壊れにくく、裏面の吸盤でテーブルや窓に付けて遊ぶこともできます。
<ワーリー スクイグズの特徴>
・音が鳴らないので寝入りにもピッタリ
・口に入れても安心な素材のクルクル回る歯がため
・カラフルな異なる形状の3種類入り
センソリーボール付 18ピースセット


センソリーボール付 18ピースセットは、でこぼこしたボールに、ブロックのようにビーズをつなげたり、つみきのように重ねたりできるフランス発のおもちゃです。
さまざまな質感・形・色で子どもの好奇心を刺激し、年齢に合わせて遊びを発展させることができるので、長い間遊べます。子どもが寝たがらない時に、一緒に布団に持っていき、眠くなるまで遊ぶのもおすすめです。
<センソリーボール付 18ピースセットの特徴>
・発達段階に合わせて遊び方がアレンジできる
・対象年齢は10ヶ月〜4歳と長く遊べる
・水に入れてOKなので、お風呂でも遊べる
ララブーム 12ピースセット


さまざまな質感・形・色のビーズをつなげたり、ねじって分けたりして遊ぶおもちゃです。
手指を刺激し五感を使って自由に遊ぶことで、子どもの考える力や応用力が育ちます。口に入れても安全な素材で作られており、洗浄・消毒もしやすいので、赤ちゃんが寝入る時におしゃぶりのように舐めてしまっても心配ありません。
<ララブーム 12ピースセットの特徴>
・口に入れても安心な素材
・対象年齢は10ヶ月〜4歳と長く遊べる
・水を入れてもOKなので、お風呂でも遊べる
子どもにとって必要性が高いお昼寝はパパ・ママにも有効
子どものお昼寝は、パパ・ママにもメリットがあります。
朝から晩まで子どもと過ごしていると、無意識のうちにずっと気を張っている状態が続きます。
子どもがお昼寝をしている間に心身を休めることで、夕方以降の家事や育児のためのエネルギーがチャージできます。
・何もせずにボーッとする
・子どもの前では食べられないスイーツを食べる
・読書や音楽鑑賞などをする
気持ちに余裕を持つために、それぞれが必要としていることに時間を費やしましょう。
なかなか自分の時間を確保できない子育て中は、意識的な息抜きが必要です。
また、疲れが溜まっている時は、子どもと一緒にお昼寝をすることで疲れを癒やすこともできます。
子どもの肌に触れながら添い寝をすると、ストレス軽減や免疫力アップの効果も期待できる「オキシトシン」というホルモンが分泌されます。
そのため、一緒にお昼寝をすることはパパ・ママにとっても有効です。
子どものお昼寝中は、パパ・ママも心身を休めるために大切な機会です。
子どもの寝顔を見ながら、自分のためにゆったりと過ごすようにしましょう。
まとめ
このページでは、子どものお昼寝の効果・お昼寝の質を高めるポイント・年齢別のお昼寝の時間の目安・スムーズに入眠するポイントなどについてご紹介しました。
子どものお昼寝は、心身の健康を保ったり、学力をアップさせたりする効果があるため、とても必要性が高いと言えます。
子どもが1日中起きていられるような体力がつくまでお昼寝は必要です。
個人差が大きいですが、3〜5歳ごろから徐々にお昼寝をしなくなるでしょう。
日中の過ごし方や部屋の環境を整えることで、お昼寝の質も高まります。
年齢に応じたお昼寝の時間を目安に質の高いお昼寝をすることは、子どもの健やかな成長につながるでしょう。




